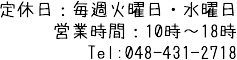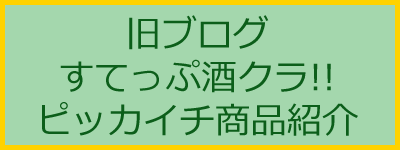日本酒の輸出といえば、そのほとんどが米国と韓国向け。この二つの国への輸出が突出しているんです。
米国では富裕層が多いためかより高級なお酒がうけて、韓国ではどちらかといえばスタンダードなクラスの日本酒がうけているようです。
この状況に仮説を立てれば、韓国の方が日本酒の市場として米国よりも成熟していて、過去には高級な日本酒もうけたのだが、その後に定着して今ではスタンダードなクラスの日本酒が普通に飲まれているということでしょうか。
では、なぜ韓国に日本酒が定着したのか?
先日、ご近所さんからキムチをいただいてその答えがよく分かった気がしたんです。
普段なかなかキムチを食べる機会はないのですが、せっかくいただいたのだからと休日に豚キムチをつくりました。子供にはあまり受けが良くなかったみたいですが、白いご飯に良く合って、ついつい食べ過ぎてしまいそうな、いい大人にはやや危険な食べ物かも知れません。
で、その豚キムチの夕飯を食べる前に料理に使って余ったキムチを、せっかくだから料理用に家に置いてあった日本酒のアテにしてみたんです。
そしたら、これがまた結構イケるんですよ!日本酒の甘さとキムチの辛さが中和してなんともいい感じなんですんね。
キムチはたぶん韓国料理の基本で、日本での醤油や味噌と同じような食品だとすれば、キムチの発酵による旨みと辛さに合う甘みを持つ日本酒が選ばれる理由が分かるような気がしました。
しかしながら、この組み合わせはお料理の味わいを際立たせるような組み合わせではなく、どちらかといえばお互いの個性ある味わいを中和させる組み合わせ。
それが酒と料理の組み合わせとして良いことなのかどうか分かりませんが、とにかく「お酒がお酒がススムくん・・・♪」みたいな組み合わせでした。
意外な発見がある韓国料理と日本酒のマリアージュは如何でしょうか?
※こちらの商品は現在取り扱いがない場合があります