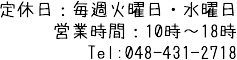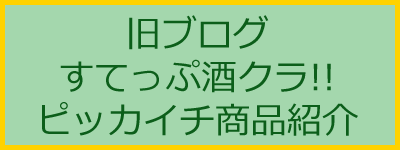「AOCコート・ド・ブール」と聞いてボルドーワインだと理解できたら大したものだと思います。かなりの通と言えるかもしれません。
そんなマニアっぽいマイナーAOCのボルドーワインではありますが、スバらしいワインがありました。
価格もボルドーワインとしてお得感があります。
【シャトー・レ・グラーヴ・ド・ヴィオ AOCコート・ド・ブール(ボルドー)】赤ワイン
ボルドーワインらしからぬラベルデザインで、味わいもいわゆるボルドーのマイナー産地のワインという感じではありません。
自然派ならではの縦に伸びる余韻が素晴らしいエレガント系と言えるワインです。
初めてコート・ド・ブールのワインを試飲したため、他のこの地のワインがどうなのかは分かりません。それでも、このコート・ド・ブールはボルドーワイン発祥の地なのだそうで、なかなか素晴らしい場所ではないかと想像されます。
輸入会社さんの資料によれば、IT業界からヴィニョロンに転じた方がビオディナミ農法により造っているワインとのこと。
比較的若いうちから楽しめる、新しいスタイルのボルドーワインと言えるのでしょう。
パリの自然派カーヴ、ワイン・バー、ミシュラン星付きレストランなどで注目されているワインなのだそうです。
魅力的な自然派のボルドーワインでした。
※こちらの商品は現在取り扱いがない場合があります
カテゴリー:ワイン